新潟みなとの歴史について知りたい
-
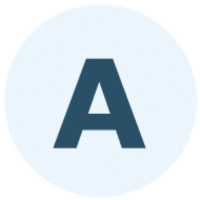 室町時代まで,越後平野で最も栄えた港は信濃川河口の蒲原津でした。戦国時代に新潟津が出現し,蒲原津は衰退しました。
室町時代まで,越後平野で最も栄えた港は信濃川河口の蒲原津でした。戦国時代に新潟津が出現し,蒲原津は衰退しました。
<近世の新潟湊>
江戸時代初め,新潟市域には,信濃川河口に新潟湊,阿賀野川河口に沼垂湊の二つの湊がありました。新潟湊は長岡藩の,沼垂湊は新発田藩の湊で,江戸時代前期,河口部の流れが変化したため,両湊町とも移転し,信濃川河口を挟んで向かい合うようになりました。両湊町は回船の寄港をめぐって争いましたが,幕府は新潟町側の主張を認め,沼垂町は勢力を失いました。
江戸時代前期に,日本海側から下関・瀬戸内海を通って大坂に通じる西回り航路ができると,新潟は繁栄し,元禄年間には日本海側屈指の湊町になりました。
天保6(1835)年と天保11年の2回,新潟湊で行われていた密貿易が発覚すると,外国船に対する防衛拠点を築くことと密輸を取り締まるため,新潟町は長岡藩領から幕府領になりました。安政5(1858)年のアメリカなど5か国との修好通商条約で,新潟は開港場の候補地の一つになりました。
<近代以降の新潟港>
新潟港は明治元年11月(西暦1869年1月)に開港しましたが,河口港で水深が浅いため,大型船が入港できず,貿易は不振でした。しかし,明治から大正にかけて,新潟港はカラフトやカムチャッカ沿岸の北洋漁業基地として発展します。
大正3(1914)年に,新潟市と沼垂町が合併します。これにより,沼垂側に大型船が着岸できるよう築港工事に取り掛かることになりました。工事は途中で県営に移管され,大正15年に完成して日本海側の代表的な港として復活します。
昭和6(1931)年9月に上越線が全通し,翌7年,「満州国」(中国東北部)が建国されると対岸航路の拠点港となります。内外貿易,旅客とも増加しますが,戦争末期には連合国軍の機雷投下により,港は機能を失います。
昭和27(1952)年,ようやく機雷掃海作業が完了し,安全宣言が出されて,外国貿易が再開されます。昭和42年に,新潟港は特定重要港湾に指定され,昭和44年には新潟東港が開港し,従来の新潟港(西港)はフェリー埠頭などがある商業・流通港として,東港はコンテナ埠頭などがある貿易・工業港として整備され,現在に至ります。
※詳しく知りたい方は『新潟湊の繁栄』(新潟歴史双書1)・『新潟港のあゆみ』(新潟歴史双書7)をご覧ください。
詳細については,歴史文化課文書館までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
文化スポーツ部歴史文化課文書館 電話 025-278-3260
■検索関連キーワード
[余暇・文化] -
- FAQ番号:B000037411
- 最終更新日:2022/01/13
-
 関連するご質問
関連するご質問
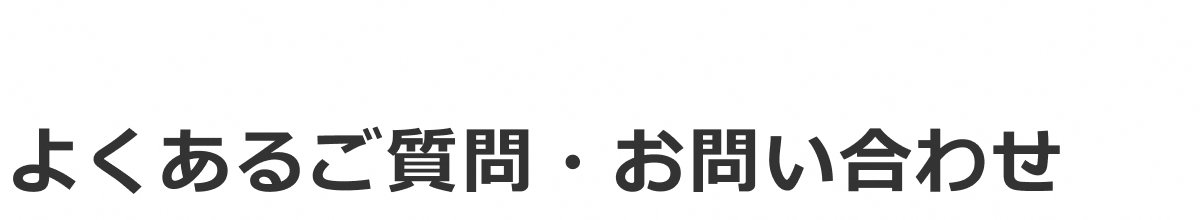
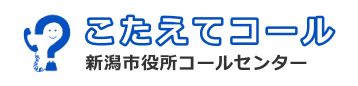




 はい
はい